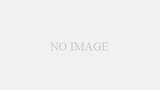※この記事はアフィリエイト広告を利用しています。
こんにちは!みんな寒さに負けないように、高垣です。
この記事を読んで頂きありがとうございます。
今日は
「易占「天地否」とは?――閉塞期に学ぶ忍耐と準備の智慧」
について私なりの見解を書いてみたいと思います。
目次
否の本質ー天地が通じないときに何が起きるのか
天地否(てんちひ)の卦は、易経64卦の中でも特に重要な意味を持つ卦の一つです。この記事では、初心者の方にも分かりやすく、天地否の卦の深い意味と実践的な活用法を解説します。困難な時期をどう乗り越えるか、その智恵がここにあります。
天地否の卦は「困難な時期をどう過ごすか」という人生の重要な課題について、深い智恵を提供してくれます。閉塞状況を嘆くのではなく、成長の機会として捉える。この転換が、天地否を乗り越える鍵となります。易占を通じて、皆さんの人生がより豊かになることを願っています。
天地否の卦は、上卦が乾(天)、下卦が坤(地)で構成される第12番目の卦です。卦の形は「☰☷」で表され、まさに天と地が分離している状態を象徴しています。
この卦の最も重要な特徴は「閉塞」にあります。
天は上に昇り、地は下に沈む。本来であれば天地が交わることで万物が生まれるはずなのに、天地否では両者が反対方向に向かい、交流が断たれてしまっています。
卦の名前である「否」は、「いいえ」「だめ」という否定の意味ではありません。むしろ「ふさがる」「通じない」という意味で、物事が停滞し、思うように進まない状況を表しています。
易経では、この卦を「小人道長、君子道消」(小人の道が長じて、君子の道が消える)と表現します。つまり、徳のない人が力を持ち、本当に優れた人が隅に追いやられる時代を示しているのです。
否の本質――天地が通じないときに何が起きるのか
天地否の卦の構造を詳しく見てみましょう。上卦の乾は、創造性、力強さ、積極性を表す一方で、下卦の坤は受容性、柔軟性、忍耐を象徴します。
この組み合わせが作り出すのは、まさに「すれ違い」の状況です。力強い天のエネルギーは上昇し、受容的な地のエネルギーは下降する。互いに背を向けているような状態なのです。
五行思想では、この卦は「土」の性質が強く現れます。
土は万物を育む母なる存在ですが、同時に重く、動きが鈍い性質も持っています。天地否の時期は、まさにこの「重さ」「鈍さ」が前面に出る時期と言えるでしょう。
季節で言えば、晩秋から初冬にかけての時期に相当します。植物が枯れ、動物が冬眠の準備を始める、生命活動が内向きになる時期です。しかし、これは決して死を意味するものではありません。次の春に向けての準備期間なのです。
卦辞に学ぶ「否」――不通・閉塞のメッセージをどう理解するか
天地否の卦辞は「否之匪人、不利君子貞、大往小来」です。これを現代語に訳すと「否は人にあらず、君子の貞に利ろしからず、大往きて小来る」となります。
「否之匪人」(否は人にあらず)は、この状況が人為的なものではないことを示しています。つまり、誰かが悪意を持って作り出した状況ではなく、自然の流れの中で生じた閉塞状態だということです。これは重要な認識で、誰かを責めたり恨んだりしても解決にはならないことを教えています。
「不利君子貞」(君子の貞に利ろしからず)は、優れた人格を持つ人(君子)であっても、この時期に正しい道を貫き通すことは困難だということです。ここでの「貞」は「正しさを貫く」という意味ですが、時には柔軟性も必要だということを示唆しています。
「大往小来」(大往きて小来る)は、大きなものが去り、小さなものがやってくることを表します。これは単に規模の大小を指すのではなく、質的な変化を意味しています。華やかで目立つものが去り、地味で実質的なものが重要になる時期なのです。
象辞の深意――天地不交が映し出す社会と人間関係の断絶
象辞は「天地不交、否。君子以倹徳辟難、不可栄以禄」です。現代語では「天地交わらず、否なり。君子もって徳を倹にして難を辟け、禄もって栄ゆべからず」となります。
「天地不交」(天地交わらず)は、文字通り天と地が交流していない状態を指します。これは自然界のリズムが乱れている状況を表し、人間社会においても正常な関係性が保たれていないことを示しています。
象辞が君子に求めているのは「倹徳辟難」(徳を倹にして難を辟ける)です。これは、徳を内に秘めて表に出さず、困難を避けるという処世術を教えています。天地否の時期には、正義感を振りかざすよりも、静かに力を蓄えることが大切なのです。
「不可栄以禄」(禄もって栄ゆべからず)は、地位や財産によって栄華を求めてはならないという戒めです。この時期の繁栄は見せかけであり、真の価値を持たないことを警告しています。
六爻の流れ――停滞から転換への可能性を読み解く
天地否の六爻は、閉塞状況の中での段階的な変化を示しています。各爻を詳しく見てみましょう。
初六:「抜茅茹、以其匯、貞吉亨」
最下位の爻は、茅(ちがや)を根ごと抜く様子を表現しています。茅は根でつながっているため、一本抜くと仲間も一緒についてきます。この爻は、同志と結束して困難に立ち向かう重要性を教えています。
六二:「包承、小人吉、大人否亨」
二爻目は「包み承ける」という意味で、寛容さと忍耐を表します。小人(徳の低い人)にとっては都合の良い時期ですが、大人(徳の高い人)にとっては試練の時期です。しかし、最終的には亨通(うまくいく)することを示しています。
六三:「包羞」
三爻目は「恥を包む」という意味で、自分の過ちや恥ずかしい部分を隠し持つことを表します。この時期には、完璧を求めず、自分の弱さを受け入れることが大切です。
九四:「有命無咎、疇離祉」
四爻目では、天命に従うことで咎(とが)を免れることができると説きます。「疇離祉」は「仲間と福を分かち合う」という意味で、協力の重要性を示しています。
九五:「休否、大人吉。其亡其亡、繋于苞桑」
五爻目は君主の位置で、「否を休める」つまり閉塞状況が終わることを表します。しかし「その亡びんその亡びん」という危機感を常に持ち、「苞桑に繋ぐ」(桑の根のように深く根を張る)ことで安定を保つ必要があります。
上九:「傾否、先否後喜」
最上位の爻では、否の状況が完全に傾き、覆されることを表します。「先ず否にて後に喜ぶ」は、最初は困難でも最終的には喜びが訪れることを約束しています。
天地否の卦の実占における卦の読み方
本卦を読む(問いの性質と現状)
天地否が本卦として出た場合、現在の状況は明らかに「行き詰まり」を示しています。仕事、恋愛、人間関係、どの分野であっても、思うように物事が進まない状況にあります。
重要なのは、この状況を嘆くのではなく、受け入れることです。天地否は自然のリズムの一部であり、必ず終わりが来ます。この時期に無理に前進しようとすると、かえって状況を悪化させる可能性があります。
占いの質問者には、まず現状をしっかりと受け止め、焦らずに時期を待つことをアドバイスします。同時に、この時期を自分自身を見つめ直し、力を蓄える期間として活用することを提案します。
変爻を見る(何がどのように変わるのか)
変爻がある場合、その爻が示す段階で変化が起こることを意味します。例えば、初六に変爻があれば、同志との結束によって状況が変わることを示します。
九五に変爻があれば、リーダーシップを発揮することで状況が好転することを表します。ただし、天地否の場合、変化は急激ではなく、徐々に起こることが多いことを理解しておく必要があります。
変爻の解釈では、その爻が持つ積極的な意味に注目します。天地否の中にあっても、変化の兆しは確実に存在しているのです。
之卦を読む(変化後の未来・行き先)
天地否から変化した之卦は、将来の方向性を示します。多くの場合、より良い状況への変化を表しますが、時には別の試練を示すこともあります。
重要なのは、之卦が示す未来は努力次第で実現可能だということです。天地否の試練を乗り越えた先には、必ず学びと成長があります。
之卦の解釈では、そこに至るまでのプロセスと、到達後に注意すべき点を併せて説明します。
まとめ
天地否の卦は、人生における重要な学びの時期を表しています。この卦が示す「閉塞」は、決して絶望的な状況ではありません。むしろ、次の段階への準備期間として、積極的に活用すべき時期なのです。
現代社会は常に変化と成長を求められがちですが、時には立ち止まり、内面を見つめることも必要です。天地否は、そうした「間」の重要性を教えてくれる貴重な卦と言えるでしょう。
この卦の教えを日常生活に活かすことで、困難な時期も有意義に過ごすことができます。焦らず、諦めず、しかし無理もせず。天地否の智恵は、現代人にとって非常に実用的なガイドラインを提供してくれるのです。
初学者の皆さんには、まず天地否の基本的な意味を理解し、実際の占いで出会った際には、この解説を参考にしていただければと思います。易占は一朝一夕で身につくものではありませんが、一つ一つの卦を丁寧に学んでいけば、必ず人生の智恵として活用できるようになります。
それでは、いかがでしたか?
易占「天地否」とは?――閉塞期に学ぶ忍耐と準備の智慧
についてのまとました。
完全解説ガイドといえるか分かりませんが、ぜひご参考にしてみて下さい 。